第九話 碧海の彼方(3)
それから、暫し放心した後、我に返ったように、ロレンソがアンドレスを見た。
「アンドレス…!
そうだった…!
そなたに、重要な客人だ!
それを伝えに参ったのだった…!!」
アンドレスも、コイユールも、ハッと己を取り戻してロレンソに向いた。
「俺に客人?
重要な…?!
こんな山奥の野営地まで、わざわざ?!」
ロレンソは、まだ先刻の件に申し訳なさげな表情を残しながらも、深く頷いた。
「わたしも、とても驚いた。
とにかく、すぐに野営場の方に戻ってくれ。
待っておられる!」
「こんなところまで来るなんて、一体…――?」
アンドレスも、そして、傍の草の上で二人のやり取りを見守っていたコイユールも、いつしか真顔になって息を詰めていた。

かくして、今宵、アンドレスを訪れた重要人物とは―――かの英国のイエズス会高僧アリスメンディであった。
英国艦隊の本団を離れて一足早く陸に向かっていた彼は、まだスペイン軍の監視の手薄いラ・プラタ副王領側の沿岸から、首尾よく上陸を果たしていたのだった。
反乱軍に渡すために英国から運んできた武器も、アリスメンディ率いる小船団によって共に陸まで運ばれていたが、さすがに、それら大量の武器まで携えて、大勢でインカ軍の陣営に向かっては、あまりに目立ってしまう。
故に、武器類は、英国兵の監視する海岸沿いの一角に、一旦、隠し置かれたまま、アリスメンディが、単身、インカ軍の陣営を目指してきた。
そして、今しがた、彼は、ついにアンドレス軍の野営地へと到着したのだった。
そこで、少しばかり時を戻し、アリスメンディ到着時の状況を見ておきたい―――。
今宵も、アンドレス軍は、ペルー副王領への進軍を阻むスペイン軍の奇襲を避けるため、険しい自然の要害に囲まれた峻厳な山岳地帯の一角に陣を張っていた。
アンデスでもひときわ標高の高い当地は、ことに夜も更ければ、早春と言えども空気は身を切るように冷たく、毛織や皮製のポンチョを着込んだ兵たちが慌しく松明や焚き火の準備に奔走している。
トゥパク・アマルの元を離れて以来、ずっとアンドレスを傍近くで支え続けている重臣ベルムデスが、そうした兵たちを見回りながら手薄を手助けしている。
すると、陣営の入り口付近から、騒然とした喧騒が聞こえてきた。
「何事か?!」
ベルムデスが急ぎそちらに向かっていくと、サッと道を開けた兵たちの向こう側に、漆黒の僧衣に身を包んだスペイン人の男が一人佇んでいる。
僧衣の人物は、俯(うつむ)き加減の顔を少し上げて、敏捷にベルムデスの方に視線を走らせると、恭しく礼を払った。
ちらりと上がった時の、その男の鋭い表情を見届けたベルムデスは、ハッと息を詰める。
(アリスメンディ殿…――!!)

ベルムデスの様子に、黒衣のアリスメンディは、再び、丁寧に礼を払うと、顔を下げたまま低い声で言う。
「お久しぶりです、ベルムデス殿。
こうして、再び、お会いできる機会に恵まれましょうとは、あの当時は、夢にも思ってはおりませんでした」
それは、非常に流麗なケチュア語だった。
突如、現われた怪しげなスペイン人が、インカ帝国の公用語であるケチュア語を、いきなり鮮やかに放ったさまに、周囲で遠巻きにしているインカ兵たちが大きく目を見開いて、耳を疑う。
それら兵たちの不審気な注視の中からアリスメンディを逃すかのように、ベルムデスは黒衣の人物に深く礼を返しながら、入り口付近から脇道へと導いた。
「まさか、このような場所まで、お見えになられるとは…!!
いやはや、わたしも、お会いできて嬉しゅうございますぞ、アリスメンディ殿!」
まだお驚きの余韻を引き摺りながらも、ベルムデスは温厚で真摯な眼差しで微笑みかける。
それから、周囲の兵たちに向くと、「このお方は怪しい者ではない故、案ぜず、それぞれ持ち場に戻りなさい」と、指示をする。
兵たちが再び散っていく様子を見届けながら、ベルムデスは、改めて、アリスメンディを見た。
十数年前まで、この南米の地にてイエズス会の神父として、そして、インカの民の解放のために果敢に活動していた――しかも、アンドレスの父ニコラスとの親交も深かった――このアリスメンディとは、ベルムデス自身も、当時、何度も面識のあった間柄である。
「本当に…こうして、再び、あなた様にお会いできますときが訪れましょうとは……!」
ベルムデスの感慨深げな声に、アリスメンディも、その闘争的な鋭い目の光を和(やわ)らげて、僅かに微笑んだ。
「トゥパク・アマル殿のおかげで、こうして再び当地に戻ってくることができました。
あなたがたが、こうしてインカの復権を賭けて立ち上がったことを、わたしは心から嬉しく思っています」
相変わらず流麗なアリスメンディのケチュア語に聞き入りながら、そこに真実の思の込められていることをベルムデスは深く察することができた。
ベルムデスは微笑んで頷き、それから温和な声音で問う。
「アンドレス様に会いに見えられたのですな?
早速にも、お取次ぎいたしましょう」
「はい。
是非にも…――」
アリスメンディは低く応えると、胸で十字を切って頭を下げた。

そうした経緯で、ベルムデスの呼びかけに応じてロレンソがアンドレスを呼びに走り――そして、不覚にも、アンドレスとコイユールの逢瀬に踏み込んでしまったわけなのだが…――。
それは、さておき、アリスメンディ到来を告げられたアンドレスは、急いで野営場へと戻ってきた。
アリスメンディがこのような場所まで来訪するとは夢にも思っていなかった彼は、すっかり驚きと興奮の表情で、相手の待つ場所まで駆け参じる。
そして、ほどなく相手の姿が視界に入ると、アンドレスは、その瞳を激しく釘づけられた。
アリスメンディは野営場の中心部からはずれた静寂な木立の一隅で、こちらに背を向けたまま、闇よりも黒々とした僧衣姿で立っている。
後ろ姿であるため表情は見えないが、森の声や風の音に聴き入っているのか、あるいは瞑想状態に入っているのか、まるで霊妙な木々と同化しているかのごとく微動だにせず立っている。
天空から降り注ぐ月明りが木立の隙間から差込み、アリスメンディの黒衣に乱反射して、まるで白い光の粒子を纏っているかのようだった。

厳粛で神々しくさえある僧の気配に、アンドレスは、一瞬、声をかけることさえ憚(はばか)られて言葉を呑む。
そんな背後の気配を察してか、ゆっくりとアリスメンディが振り向いた。
その全身に纏う崇高な雰囲気からは予想もつかぬほどに、僧と言うには、あまりに鋭利な眼差し――アンドレスは、再び息を詰める。
一方、アリスメンディは、ゆっくりと目を細めて、むしろ懐かしそうにアンドレスを見つめた。
「これは、アンドレス殿。
あどけない子どもだったそなたが、今は、このような立派な若者に成長していようとは」
「え…!
アリスメンディ殿…昔の俺のことを覚えておいでなのですか?」
やや緊張した真剣な面差しで問うアンドレスに、アリスメンディは微笑して応える。
「そなたの父とわたしが、親しき友であったことは聞いておろう?
幼き日のそなたとは、もちろん、幾度も会っている。
覚えておられぬか?
そなたと傍近くあったのは、せいぜい4〜5歳頃までであったろうか…。
ならば、そなたの記憶にはなくても無理からぬことではある。
あの頃は、そなたは、やんちゃな子どもで、そなたの父上も母上も、ずいぶん手を焼かされていたものだった。
わたしにも、よく遊んでくれとせがんでいたではないか」
「…えっ……!」
自分さえ忘れている幼少時代の様子に触れられて、咄嗟にアンドレスは耳元を紅潮させた。

過去から現在までの全てを見透かされているかのような戸惑いと照れ臭さの感情に覆われつつも、しかし同時に、アンドレス自身も、何故か不思議と懐かしい感覚に憑かれずにはいられなかった。
(こうしていると…確かに…ずっと以前、俺は、アリスメンディ殿に会っていると感じる…!
さっき、偶然にも、亡き父上と思わぬ再会を果たしたばかりだからなのか――?
いや…父上は、アリスメンディ殿の到来を知っていたからこそ、今夜、現れてくれたのだろうか?!)
遥か遠くに忘れ去っていたはずの過去の記憶の断片や様々な感情までもが、心の奥から泉のごとく溢れ出す感覚に、アンドレスの胸は熱く込み上げる。
澄んだ大きな瞳を揺らしている彼に、アリスメンディは、ゆっくりと深遠な声音で語りはじめる。
「アンドレス殿、いつかはこのような日が来るかもしれぬとは思っていた。
トゥパク・アマル殿の志を継ぎ、そして、そなた自身の父の遺志をも継ぎ、今、ここにいるそなたと、こうして見(まみ)えることができたことは、わたしにとって無上の喜びなのだよ。
既に聞き及んでいると思うが、そなたの父も、スペイン人でありながら、インカの人々の解放に命を捧げた」
「アリスメンディ殿…俺は、最近まで、父のことは殆ど何も知らずにおりました。
この反乱に加わったのも、父の遺志などとは、全く思いもよらぬままに……」
「それでは、そなたは、自然と、その方向に導かれていたのだな。
そなたの中に宿る、亡き父上が、そうさせているのか…。
こうしていると、まるで若い頃のそなたの父自身と、共にいるように思えてくる」

「父上と俺は…そんなふうに、似ていますか?」
「ああ、とてもよく似ている……」
アリスメンディの声は、微かに詰まった。
そして、それを隠し呑み込むように横を向くと、暫し沈黙になる。
そのような彼の傍で、アンドレスも、いっそう胸がいっぱいになってくる。
ベルムデスからアリスメンディのことはいろいろ聞かされていたし、ましてや、あのトゥパク・アマルがあれほど重要な書状を出すほどの相手なれば、この眼前のアリスメンディが信用に値する人物であろうことは、アンドレスには頭の中では十分に理解できていた。
だが、これまでの彼は、心の奥底では、完全には不審の念を払拭できずにいたことも事実である。
アリスメンディは、いかに過去の深い事情があるとは言え、現在は、英国王室に縁の深い高僧なのだ――。
しかも、当地に進軍する英国艦隊に乗り組み、その上、スペイン人で……挙げれば、不審の種は切り無くあった。
だが、今、こうして間近で接しているうちに、アンドレスは、意識や理屈を超えたもっと深い次元で、アリスメンディとの、何か絆のようなものの存在を次第に感じはじめていた。
(昔、子どもの頃に良くしてもらったからなのか…?
それとも、俺の中に流れる父上の血がそう感じさせるのか……)
まだ何も知りもしないのに心許していく己自身に戸惑いながら、彼は、やや躊躇(ためら)いがちな眼差しで、相手の横顔をそっと見つめた。

「俺の天幕で、ゆっくり話しでも…?」
うかがうように言葉を継いだアンドレスに、アリスメンディは僅かに微笑む。
そして、いっそう冷気の増した深夜の風を、胸に深く吸い込んだ。
白い清涼な月明りが、彼のスペイン人らしい彫の深い輪郭に、音も無く降り注ぐ。
「いや、外気が心地よい。
この界隈を歩きながら、話しても良いだろうか?」
実直な相手の声に、アンドレスも素直に頷いた。
「はい。
では…」
「アンドレス殿…いや……」
ふっとアリスメンディが、苦笑する。
「え?」
「いや…」
アリスメンディは、暫し言葉を探しあぐねて間を置いていたが、やがて軽く咳払いをしてから、「アンドレスと呼んでも?昔は、そう呼んでいたので…」と、アンドレスの横顔に向いて、はにかんだ。
「あ…はい!
それは、もちろん…!」
「ありがとう、アンドレス」
そう言うと、アリスメンディは夜露に湿る若草の上を、ゆっくりと歩みはじめた。
長い僧衣の裾が、草の上で静やかな衣擦れの音を立てている。
それに聞き入るように横を歩みゆくアンドレスに、不意にアリスメンディが問いかけた。
「アンドレス、そなたは此度の英国軍の到来の背景を――つまりは世界情勢を、どれくらい知っているかね?
この国では、特に、そなたたちインカ側の者たちには、海を隔てた世界の動きは、なかなか伝わりにくいものであろう?」

世界情勢――これまで、この植民地内でのインカ側とスペイン側の敵対的関係のみに目を奪われてきたアンドレスにとって、アリスメンディの問いかけは、予想を超えた、即座には返答しようのないものだった。
アンドレスは言葉に詰まってから、やがて居住まいを正して、率直に応える。
「いえ…国際情勢のことは、俺は殆ど把握できていなくて…。
英国とスペインが敵対的な関係にあることは、さすがに俺も、ある程度なら知っていますが…」
「ならば、もっと知っておかねばなるまい。
あのトゥパク・アマル殿が、わざわざ英国艦隊に白羽の矢を立てたのは、それなりの理(ことわり)があってのことだと私には思える。
もちろん、英国とスペインとの敵対関係を見通してのことであろうが、その二者だけを見ていては、トゥパク・アマル殿の真意も、全体をも、見損なう。
アンドレス、そなたは、もっと視野を広げて考えてみたことはあるかね?
何故、今、このタイミングで、英国艦隊なのか――その背景を…いや、歴史を、と言うべきか」
「トゥパク・アマル様が、英国艦隊を呼び寄せたことの…背景……歴…史?」

「アンドレス、そなたの言うとおり、スペインと英国との因縁は深い。
だが、それも、そなたたちのインカ帝国が――いや、もっと厳密には新大陸が、発見されたことと、無縁ではないのだ」
「!……」
反射的に顔を歪めたアンドレスに、アリスメンディは独り言のように低く呟いた。
「もちろん、そなたたちには罪は無いことだが」
「――……」
「アンドレス、そなたが、どこまで知っているかは分からぬが、この新大陸から手に入れた財宝や収穫物を巡っての英国とスペインの争奪戦は――インカ帝国が侵略されて既に200年以上になろうが、それと同じほどの期間、延々と続いてきた。
もっとも、当地を我が物にしたスペインだけに甘い汁を吸わせまいと躍起になっていたのは、英国だけではなく、フランスも同じだったが。
だが、あのアルマダの海戦で、当時、『無敵艦隊』とまで言われたスペイン艦隊を英国が打ち破ってからは、英国は他のヨーロッパ諸国の追従を引き離し、かつてのスペインを凌ぐ勢いで海軍力を伸ばしてきた。
しかし、そのことで、余計に問題は複雑になったのだ」

アンドレスが固唾を呑む脇で、アリスメンディは、さらに続けていく。
「あのアルマダ海戦の後の英国は、軍事力と制海権を駆使して、スペインの船団を次々と襲ったのだ」
「襲った?!
それは、海戦を繰り返したっていうことですか?」
「いや、それなら、また流れは変わったかもしれぬ。
だが、実際には、多くは表立った軍事行動ではなかったのだ」
「え?
戦ではないのに、襲ったって…?
っていうことは…!…海賊……?!」
「そうだ。
海賊を利用しての略奪行為だった――しかも、英国王室のお墨付きのね」
「――!!」
「言ってみれば、英国王室は、スペイン船からの略奪を正当な戦闘行為と見なしていたというわけだ。
実際、そうした海賊行為に、ナイトの称号まで出していた時代も、そう昔のことではない」
次第に皮相な声音に変わっていくアリスメンディの横で、アンドレスの口の端も苦々しく歪んでいく。

暫し、各々、重く思いに耽った面差しで無言のままに歩んでいたが、やがてアリスメンディが再び口火を切った。
「アンドレス、何故、あのアルマダの海戦が起こったか知っているかね?」
「いえ…あまり詳しいことは」
「皮肉なことだが、あの海戦にも、この植民地がかかわっている。
アルマダの海戦は、インカ帝国侵略後のおおよそ50年後だが、結局は、この植民地からの収奪物を巡っての因縁に端を発しているのだ。
あの海戦の発端は、スペイン艦隊が英国に侵攻したためだった。
だが、もとを正せば、スペインがそこまでしたのも、英国の海賊船の取り締まりをエリザベス女王に申し入れたところを、女王に拒まれたことによるのだ」
「…――!」
思わず絶句するアンドレスの表情を見やりながら、アリスメンディも息を継ぐ。
そして、次第に白みゆく上空に視線を投げた。
「全く、そなたたちが聞けば、空いた口も塞がらんだろうが、植民地の人々が血を吐く思いで使役されている傍ら、そこから絞り取った収奪物を巡って、西洋諸国の間で延々と争いが繰り返され…――そして、今も、それは、熾烈を極めながら続いているというわけだ」

アリスメンディの言葉に、アンドレスは険しい目つきで唇を引き結んだまま、じっと聞き入っている。
一方、アリスメンディは指先で胸の十字架に触れると、さらに先を続けていく。
「あのトゥパク・アマル殿は、そうした世界情勢も、かなりの範囲まで把握していたものと思われる。
この国で大規模な反乱が起こり、そのせいでスペイン側が鎮圧に腐心していると知れば、もともと喉から手が出るほど当地を欲していた英国が、これは好機とばかりに動き出さぬはずはないと――そんなことは、彼でなくても予測できることだ。
だが、多分、彼は、さらに、その先まで情勢を読んでいた」
「その先?!」
「英国の情勢だ。
英国とて、決して、今は、万全な状態では無い。
そのことを、恐らく、トゥパク・アマル殿は把握していたのだ」
「!!…――」
真剣な眼で喰い入るように己を見据えるアンドレスに、アリスメンディは瞬間的に視線を走らせると、微光を帯びた天空を再び振り仰いだ。
早朝の冷風の中で、僧衣の裾が音を立てて翻る。
他方、アンドレスも、纏うマントの裾を向かい風に吹きなびかせながら、大きく一歩、アリスメンディの方に踏み込んだ。
「英国の情勢とは、どういうことです?
英国は世界最強の海軍力を誇る、スペイン軍を凌ぐ強敵と思っていましたが……!」
やや興奮気味に己に迫り来るアンドレスに、アリスメンディは彫りの深い横顔を向けたまま、低く沈着な声音で応える。
「もちろん、そなたたちにとっても、スペイン軍にとっても、厄介な強敵であることには変わりはあるまい。
だが――このような時代、事情を抱えていない国の方がむしろ珍しかろう?」
そう言って言葉を切ったアリスメンディの横顔は、鋭く天空を睨み据えているようでもあり、それでいて、どこか微笑を湛えているようにさえも見える。
アンドレスは表情の読めぬ相手の輪郭に釘付けられたまま、強風の中で息を詰める。
やがて、アリスメンディは、ゆっくりと視線をアンドレスの方に戻した。
「確かに、英国海軍は、現在の時点では、世界一と言えるほどに戦闘能力も装備も良い。
その英国艦隊に総力上げて押し寄せられては、たとえ当地のスペイン側が英国に破れても、今度は、インカ側が英国の侵攻を受けるリスクが非常に大きくなろう?
だが、それでは、そなたたちにとっては支配者が変るだけで、植民地であることは少しも変わらず、全くの本末転倒だ。
しかし、今の時期なら、必ずしも、そう事は運ばぬと…――あのトゥパク・アマル殿は見極めていたのだと、私には、そう思える」

「では、今は、英国も、当地に総力は上げられない状況にあると?!
英国も、何か問題を抱えているのですか?!」
「英国の敵は、もともとスペインだけではない。
昔も今も、英国とて厄介な相手には事欠かぬ。
最近のところで、そして、そなたたちの身近と言えば身近なところでは、この同じ新大陸の北米でも、植民地側と、そして、植民地の利権を握ってきた英国側との対立が激化している。
北米で本格的な独立闘争が勃発したのは、もう5年ほど前の話だが、むこうでは、今は植民地側の形勢が有利にあるのだ」
「え!!――独立闘争ですって?!」
アンドレスは己の動悸の速まるのを抑えきれずに、半ば叫ぶように声を上げていた。
「北米でも、植民地支配からの独立闘争が…?!
しかも、この、今の、同じ時期に――?!」

そんな昂ぶるアンドレスを諌(いさ)めるように、アリスメンディはいっそう低めた声で淡々と言う。
「だが、当地のそなたたちとは違って、北米の場合は、独立運動の中心は植民地に住まう白人たちだ。
だから、そなたたちのような、生粋のその土地の民による反乱とは、趣はだいぶ異なっている」
それでも、アンドレスは興奮と恍惚に表情を輝かせる。
「ですが、植民地支配体制からの独立という点では、一致していますよね?!
それで…?!
アリスメンディ殿!
それで、北米の独立運動は、どんな状態になっているのですか?!」
「北米での英国軍と植民地軍との武力衝突は、結果的には、植民地軍に優勢に推移してきた。
つまりは、植民地支配を敷いてきた英国は、徐々に植民地への支配力を削(そ)がれてきているのだが――そうした英国側の苦境に目をつけたのが、もともと英国への因縁が深いフランスだった」
「むこうでは植民地軍が優勢に…!!
そ、それで?!
英国は、フランスとも、確執があるのですか?!」
「フランスと英国は、昔から北米での利権を争い続けてきた間柄だ。
そのフランスが、植民地軍に劣勢を来たしはじめた英国の状況を見過ごすはずはない。
そして、実際に、フランスは、この時とばかりに英国に宣戦布告した。
それが、今から、ほんの2年程前のことだ。
そなたたちの、この南米を巡っての、スペインと英国の争奪戦と似た構図が、北米でも、英国とフランスとの間で展開してきたというわけだ。
そして、その闘争は、今、この瞬間も続いている」

アンドレスは、暫し、言葉も失って呆然と宙を見た。
辺りには、いつしか夜明けを告げる鳥の声が、遠く、甲高く、響きはじめている。
夜明け前の極寒の中にあるこの時間――にもかかわらず、身を切るような冷気の中で、アンドレスの頬は、興奮と驚愕とで、すっかり上気し、熱く火照っていた。
「そんなことが…この同じ大陸の反対側で、起こっていたなんて……!」
他方、アリスメンディは、冷ややかなほどに淡々たる表情を変えず、ただ苦笑する。
「そのように驚くほどのことではなかろう。
いずれの植民地でも、それほどに搾取が甚(はなは)だしく、それを支配する側も、植民地の民を思う心など無きままに、他の列強から我が物を奪われまいとだけ必死になってきた結果だ。
むしろ、全ては、起こるべくして起こっている」
「アリスメンディ殿……」
「全く、世界中、あっちもこっちも、ゴタゴタには事欠かぬ。
ともかく、独立闘争という北米での扮装絡みで、英国は、結果的に他のヨーロッパ諸国に対して海上封鎖という策に出た。
それが、えらく反感を買ったのだ。
結果、英国は、ロシアやプロイセン、ポルトガル、北欧諸国にまで睨まれるようになった。
それが、まさに、英国の今の情勢だ。
ただでさえ、スペインやフランスと険悪だった上に、今、それらの国々からも孤立している英国が、どれほど予断のならぬ戦々恐々たる状況にあるか、アンドレス、そなたにも想像できよう?
そんな英国が、いくら当地で、そなたたちインカ軍が暴れてスペイン側が苦心している好機とはいえ、この南米の地の攻略に、今のこの時期、総力を上げられるような余裕なぞないのだ」
そこまで話し終えると、アリスメンディは、鋭い眼差しでアンドレスを改めて見据えた。
アンドレスは吸い込まれるように、アリスメンディの冷徹なほどに鋭利な瞳を見つめる。
いつしか二人は、今、まさに昇りつつある太陽の見渡せる、険しく切り立った断崖上に立っていた。
二人の前には、黄金の陽光に染め上げられゆく清冽なアンデスの霊峰が、どこまでも果てしなく展開している。
それら峰々の斜面には、まだ随所に白く輝く雪が残っていた。
それら雪面直近を、朝陽を受けて煌く金粉のごとく雪煙を舞い上げながら、漆黒のコンドルが滑空している。
アンドレスは、眩しそうに目を細めた。
「トゥパク・アマル様は、それら全てを知っていて、此度の策を……!」

アリスメンディもまた、強靭なコンドルの飛翔を目で追いながら、低く呟く。
「アンドレス、わたしが、今、そなたに伝えてきたように、英国は、この南米以外にも、戦力を回さなければならぬ場所が数多くある。
実際、此度の、当地へ派遣された英国軍の規模は――それ相応の軍艦をよこしてはいるものの、当地のスペイン側を圧倒するほどに充実した戦力かと言えば、甚だ疑わしい。
対するスペインは、かつてほどの海軍力の威光は薄れているとはいえ、今でも決して弱小な相手ではない。
当地のスペイン側とて、英国なり、どこぞかの西洋諸国が、不意に攻め込んでくる可能性を、これまでも度外視はしていなかったはず。
つまりは、それなりの備えは、スペイン側にも、既にあると見積もっておいた方が現実的であろう。
然るに、当地で奮える各々の戦力を鑑(かんが)みれば、今の両者が激突すれば、勝敗は、どちらに転ぶか全く分からぬ。
そなたが察しているように、恐らく、トゥパク・アマル殿は、そこまで読んでいた。
今の英国が当地に派遣できるのは、当地のスペイン軍と共倒れしてくれる程度の、ほどほどの戦力であろうとね…――。
一見すれば、あまりに無謀に見えるトゥパク・アマル殿の此度の計略だが、実は、世界情勢まで視野に入れて仔細に計算されたものだと、わたしには思える」
(トゥパク・アマル様……!)
アンドレスは、心の奥で恍惚と呟く。

そんな彼に、畳み掛けるようにアリスメンディは続ける。
「とはいえ、英国軍も、スペイン軍も、強敵であることには違いなく、そなたたちインカ側にとっても、一縷の予断も許されぬ相手に変わりはあるまい。
この先、この三つ巴(みつどもえ)の争い、一体、どう転がっていくのか、もはや、わたしにも先は読み切れぬ」
武者震いなのか、緊迫感からなのか、わななく拳を握り締めて立ち尽くすアンドレスに、アリスメンディは、横顔のまま敏捷に視線を走らせる。
「アンドレス、そなたも、これで分かったであろう?
実際のところは、英国も悠長なことをやっている余裕なぞ、少しも無い状況であるということが。
そして、英国の狙いも……。
トゥパク・アマル殿の呼びかけに、反乱軍を援護する正義の味方のような顔をして参上した英国艦隊だが…――その腹の内は、スペインにも負けず劣らず、ということだ。
此度の英国軍総指揮官ジョンストン提督は、一見、紳士的な男ではあるが、その腹の内では、当地のスペイン制圧は当然ながら、ひいては、この植民地の支配権の強奪に執念を燃やしている。
いかに英国も事情を抱えているとはいえ、あの提督の指揮する英国艦隊は、スペイン側にとっても、そなたたちにとっても、決して甘い敵ではなかろう」
「――アリスメンディ殿…!」
アンドレスは、真っ直ぐアリスメンディの横顔に向き直った。
そして、意を決したように、思い切って問う。
「これまでに様々なご事情や経緯があるとはいえ、アリスメンディ殿は、今は、英国側の一人でありましょう?
これほどに、内情を、俺に話してしまっていいのですか?」
アリスメンディは、僅かに苦笑する。
「ふ…内情も何も……。
これは、あくまで客観的な事実にすぎぬ。
とはいえ、確かに、そなたが想像している通り、この新大陸からも、スペイン本国からも追放されたわたしを受け入れた英国や英国王室に、何の恩義も感じていないと言えば嘘になるが――」
「え…――!」
アリスメンディの返答に、アンドレスは返す言葉に詰まって、言葉を呑んだ。
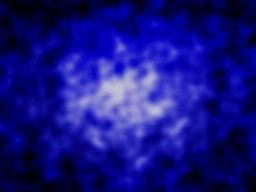
他方、不意に、アリスメンディは、昇りゆく太陽の眩い光を避けるかのように、スッと太陽に背を向ける。
いきなり真正面に向き直られる形となり、アンドレスは、やや後ずさった。
逆光になったアリスメンディの漆黒の僧衣は、今までにも増して深い地底のごとく黒味を増し、影になった顔の面差しも、ひどく分かりづらい。
そんな相手の表情を読み取ろうと懸命に目を凝らすアンドレスに、今度はアリスメンディの方から、一歩、近づいた。
そして、アンドレスの耳元で囁くように問う。
「アンドレス…わたしは、わたしが知っていることは、そなたに伝えた。
さあ、今度は、そなたの番だ。
――トゥパク・アマル殿が、脱獄したという噂は本当か?
脱獄した彼は、今、どこにいる?」
「え?!」
反射的に、アンドレスは、さらに一歩、退いた。
彼の目の前で、アリスメンディの僧衣が風の中で大きく翻り、強風に煽られる胸元の十字架が不規則に陽光を反射して、鋭い閃光を放っている。

「アンドレス、今や英国王室に近しい間柄となり、英国軍の相談役として渡来したわたしを、さすがのそなたでも、本心では、信じきれぬか?
確かに、わたしが、英国のために、そなたを取り込もうとして親切を装っていると疑うこともできよう。
だが、わたしは…――いや、イエズス会というものが、元々そうであるのだが――特定の何処かの国への帰属意識などとは無縁なのだ。
神の御心が果たされることのみを願う、ただそれだけだ」
「アリスメンディ殿…――」
アンドレスの後退する足が力を抜かれたように、その場に止まる。
アリスメンディは、差し射るような鋭利な、そして、厳粛でさえある眼差しで、アンドレスの瞳を貫いた。
「アンドレス、わたしは、昔も、今も、この内面は何も変わってはいない――。
かつて、この地に、そなたの父と共にありしあの頃と……。
わたしの言っている意味が、分かるかね?
今でもわたしは、英国側でも、もちろん、スペイン側でもなく、そなたたちインカの民と共にありたいと願っている。
いや…わたしが、そうありたいというのではなく、それが神の御心だからだ」
「――アリスメンディ殿」
「そなたたちの力になりたい。
わたしを信じてくれないか」
「俺は……」
無意識のうちに唇をきつく噛み締めたまま、アンドレスは、縋(すが)るような思いで亡き父からの言葉を待っていた。
しかし、先刻はあれほどハッキリ聴こえたはずの父の声は、今は、彼の脳裏にも、心にも、一片も響いてはこない。
(父上…!
俺自身に判断しろと言っているのですか――…?!)
鋭利なアリスメンディの視線に貫かれたまま、しかし、今度は、アンドレスも決然とアリスメンディの深い漆黒の瞳の奥を見返した。
その瞳の底の底まで真っ直ぐに見据えくるアンドレスに、アリスメンディは、納得するまで相手の為すに任せるがごとく、微動だにせず立っている。
見据え合う瞳の奥に、互いの魂を映し取るかのような長い時の中で、アンドレスの心の眼は、相手の内奥に、音もなく燃え上がる清浄な蒼い炎の気配を感じ取っていた。

アンドレスは息を詰めて、その気配に、研ぎ澄まされた全神経を集中させる。
いつしか胸を強く押さえ込んでいた手の平に、己の心臓が加速しながら打ち鳴っているのが伝わってくる。
(この気配――どこかで感じたことがある…?
トゥパク・アマル様?…父上?……それとも、俺自身の中に……?!)
暫しの間、逸(はや)る胸の鼓動のおさまるのを待った後、アンドレスは意を決した眼差しで、アリスメンディに真正面から向いた。
「わかりました。
俺は、あなたを信じます…!!」
「アンドレス…――」
アリスメンディの逆光になった面差しに、読み取れぬほどの微かな笑みが浮かぶ。
他方、アンドレスは、真っ直ぐ大地に立ちなおすと、実直な声で言う。
「先ほどの質問の答えですが、トゥパク・アマル様は無事に脱獄を果たしておられます」
「そうであったか…やはり……!」

唸るように低くそう応えると、黒衣の僧は、だいぶ高く昇って薄い雲の陰に入った太陽に視線を向けた。
「それで、彼は、今、どこにいる?
スペイン側は、脱獄の事実を認めてはいないようだが」
「トゥパク・アマル様の居場所については、俺もハッキリしたことは分かっていないのです。
でも、とうの昔に牢を抜けているのは事実です。
俺は、トゥパク・アマル様から、ご無事を記した直筆の書状も受け取っていますから。
今頃は、多分、叔父上の陣営…というか、ペルー副王領のインカ軍本隊に内々に戻られているかと」
「叔父上?――トゥパク・アマル殿の従弟、ディエゴ殿のことか?」
「はい。
叔父上は、トゥパク・アマル様が囚われた後、インカ軍の本隊をあずかっておりました。
脱獄直後は、トゥパク・アマル様は別の場所に身を隠しておりましたが、さすがに英国艦隊到来も迫った今ともなれば、本営に戻られているはずです。
民の間には、まだ、姿を現してはおりませんが」
「そうか」
アリスメンディは、鋭い眼で地面を見据えた。

「それで?
そなたは、ここの部隊を率いて、これからトゥパク・アマル殿のいるであろう本隊へと合流する予定か?」
アンドレスは、きっぱりと頷いた。
「はい。
ここまで来れば、そう遠くはないはず。
近いうちには、合流できるはずです!!」
「それでは、わたしも同行させて頂きたい」
「え…!?」
再び驚いた声を上げるアンドレスに、アリスメンディは変わらぬ表情のままに言う。
「わたしは英国側の内情にも通じている。
そなたたちにとって、何かと役に立てる部分もあろう」
「で…でも……」
「アンドレス、やはり、わたしへの疑いを拭えないかね?
繰り返して言うが、わたしは、そなたたちの力になりたいと欲している。
なに…どうせ、わたしは、武器のひとつも持ち合わせてはいない。
いざとなれば、このような丸腰の僧の一人、そなたの腕なら、いつでも切り捨てることなど容易(たやす)かろう。
わたしの動向に怪しきことあれば、いつでも、そうするが良い」
「なっ…!
そのような…切り捨てるなんて……!!」
アンドレスは、暫しの間、険しくも真剣な顔でアリスメンディをじっと見た。
それから、噛み締めるように言う。
「わかりました…!
アリスメンディ殿、俺は、あなたを信じると言った。
あなたが望むのであれば、ご同行ください」
アンドレスの返答に、アリスメンディは逆光に翳(かげ)った面差しのままに微笑した。
「それでは、話は決まった――。
ありがとう、アンドレス」
胸元で十字を切るアリスメンディと、礼を払い返すアンドレスとの間を、早朝の身を切る冷風がビョウと唸りながら駆け抜けていった。

次第に太陽が高く昇りはじめると、今まで忘れ去られたような静寂の中にあった二人のいる断崖上の麓(ふもと)には、徐々にインカ兵たちの往来が増してくる。
早朝の任務のために行き過ぎていく兵たちは、皆、高所に立つ見慣れぬスペイン人神父の姿にハッと息を詰めた。
しかし、その神父の傍にいるアンドレスの姿を認めると、遠目から二人に丁寧に礼を払って去っていく。
やがて、それら兵たちの間からロレンソが姿を現し、断崖上に立つアンドレスとアリスメンディの方へと、真っ直ぐ斜面を登って来た。
他のインカ兵たちに比して、明らかに風貌も身なりも逞しく高貴に際立っているロレンソの全身に、アリスメンディは鋭い視線を走らせる。
ロレンソも、また、己自身にも負けず劣らず非常に鋭利な目をした眼前の僧に、敏捷な視線を走らせた。

アンドレスはロレンソの方に軽く手を上げて笑顔で招き入れると、アリスメンディに向いて紹介する。
「アリスメンディ殿、こちらはロレンソ。
インカ軍結成初期から参戦している我が軍の幹部です。
俺の神学校時代からの朋友でもあります」
そして、ロレンソの方にも向くと、「こちらがアリスメンディ殿。トゥパク・アマル様が書状をお送りしたお相手だ」と、紹介した。
「ロレンソです。
お目にかかれて光栄です」
鋭い視線を伏せて丁寧に礼を払うロレンソに、アリスメンディも胸で十字を切って礼を返した。
やがて、顔を上げると、ロレンソは素早くアンドレスに視線を向けた。
「アンドレス、そなたに火急の用件が」
「また、俺に火急の用件?!
こんな早朝に?!」
目を瞬かせるアンドレスに、ロレンソは早口で急(せ)くように言う。
「ああ。
とにかく、わたしと共に来てくれ」
ロレンソの鋭い口調に押されるように、アンドレスは本営の方へと足を戻しかけながら、アリスメンディを振り向いて慌てて礼を払う。
「では、また後ほど!
アリスメンディ殿の身の回りのことなど、手配しておきますので!」
ロレンソに引きずられるようにして、急ぎ引き返していくアンドレスに礼を返しながら、無言のままに、アリスメンディは去り行く二人を見つめた。
足早に陣営中心部に引き返しながら、アンドレスは、いつにも増して鋭利な目つきで脇を歩み進むロレンソを見た。
「ロレンソ、俺に火急の用って、今度は誰なんだ?」
「――わたしだ」
「え?!」
アンドレスは驚いて、友の横顔を凝視する。
一方、ロレンソは俊敏に背後を振り向き、アリスメンディの姿が遠く離れていることを確認すると、アンドレスの背を強く押しながら大木の陰へと寄った。

「ロレンソ…?!」
「アンドレス、そなた正気か?!
アリスメンディ殿を我々と同行させるなど!!」
総じて沈着なはずのロレンソが、ひどく険しい形相で迫り来るように詰めてくるさまに、瞬間、アンドレスは凝固して息を呑む。
が、すぐに我に返って、彼も険しい目つきでロレンソを見返した。
「ロレンソ…――どうして、それを?!
まさか、俺たちの話を盗み聞きか?!」
「人聞きの悪い言い方をするな!
あのような場所に、あのような状況で、護衛も付けずにいるそなたを一人にできようか!
いつ、どこから、敵方の密兵が躍り出てくるかも分からぬのに!
いや、そのようなことより、アリスメンディ殿のことだ。
我が軍に同行などと、そのような無茶なことを…!!
そなたは、我々の動向を、逐一、英国艦隊に筒抜けにさせる気か?!」

「ロレンソ……!
アリスメンディ殿は、真にインカのことを思って、此度の同行を申し出てくれている!!
そのような、まるでスパイ呼ばわりをするとは…!!」
本気で憤っているアンドレスの様子に、さすがに大人びたロレンソは、慎重な面差しに変わって、言葉を選びはじめる。
「アンドレス、わたしの言い方が不味かったなら、謝る。
だが、今の状況では、どんなリスクも排除すべきではないのか?
アリスメンディ殿は、確かに、トゥパク・アマル様さえ信頼しているお方だ。
そなたの言うとおり、信用できるとは、わたしも思う……。
だが――万一の可能性は否定できまい?
言いにくいことだが…英国側の密偵の一人だとしたら、どうなる?!
まもなく、我々は、トゥパク・アマル様の元に到着するというのに――!!」
「――ロレンソ!」
決然と友の言葉を遮って、とはいえ、今はアンドレスも激昂をおさめ、真摯で真剣な瞳になって相手の顔を見据えた。
「ロレンソ、君が我が軍のことをどれほど案じているかは、痛いほど分かっている。
だけど、アリスメンディ殿だって、真にインカのことを思っていると俺には分かる。
彼の思いを堰き止めたくないんだ。
それに…――必ず、俺たちに力を貸してくれるという確信が俺にはある!」
「――……!」
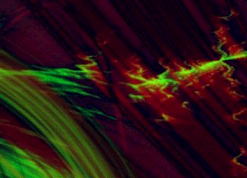
二人は鼻先まで顔を付き合わせたまま、互いを激しく凝視する。
頑固なほどに、あくまで意志を曲げようとしないアンドレスに、ロレンソは胸の奥で息をついた。
「――アンドレス、何故、そこまで言える?」
「分からない…!
だけど、そう思うんだ――…!」
「アンドレス…そなたの気持ちは良く分かった。
だが、もう一度だけ考えてみてくれ。
アリスメンディ殿の同行を許すことは、つまりは、トゥパク・アマル様の居場所をわざわざ英国側に教えてやるようなものではないのか?
そうなれば、トゥパク・アマル様のお命さえ、危険に晒すことに……!」
しかし、アンドレスは、そんなロレンソの言葉さえもきっぱりと退けた。
「それは、アリスメンディ殿が密偵だったら、という前提で言っているよな?」
「――例えばの話だ……!
だが、絶対にありえぬとは言えぬ」
「俺はアリスメンディ殿を信じている。
だから、彼が密偵だなどと言われれば、やはり聞き捨てならない。
だけど…――だけど、ロレンソが言うように、万一にも、アリスメンディ殿が英国側の密偵だとしたら――それなら、俺は、彼が完全に一人でここまで来たとは思えない。
他の英国側の斥候たちも、密かに、その辺りをうろつき、今、この瞬間にも、俺たちの動向に目を光らせているはずだ。
それなら、アリスメンディ殿が俺たちに同行しようがしまいが、そんなことには関係なく、英国側の斥候は、この先、密かに俺たちの行軍を追跡してくるに違いない…!
これから俺たちがインカ軍本隊に合流する以上、トゥパク・アマル様の居場所が英国側に知れるのは、どのみち避けられまい。
だから…俺たちにできるのは、たとえ居場所が知られようが、トゥパク・アマル様の陣営を絶対に攻め落とさせないこと――!!
いや、それ以前に、断じて英国軍の上陸を許さないことだ……!!」
「アンドレス……」

これまで見せたことのないほどに頑として譲らぬ友の姿に、ロレンソも、今はそれ以上は言えず、黙るしかなかった。
ロレンソの目には、何故、ここまでアリスメンディの肩を持つのか、アンドレス本人が己自身を持て余し、突き上げる感情に翻弄されているようにさえ見える。
ロレンソは友の肩を握り締めると、俯(うつむ)きがちになった相手を見下ろした。
「アンドレス…そなたがそこまで言うなら、やむを得まい。
ならば、わたしをアリスメンディ殿の傍につけてくれ。
それくらいなら、わたしの言うことも聞き入れてくれるな?」
「ロレンソ……」
不意に訪れた静寂の中で、頭上の木々のざわめく音がする。

やがて、アンドレスは黙って頷いた。
「ありがとう、アンドレス」
友の肩を握り締める腕に力を込めながら、ロレンソも、しかと頷き返した。


